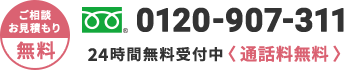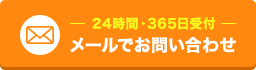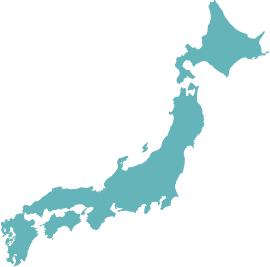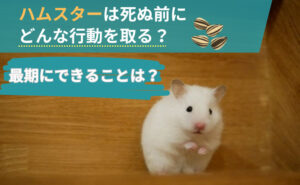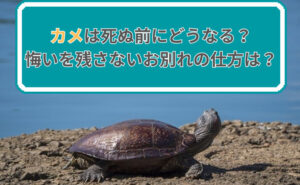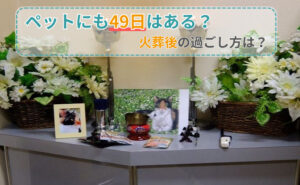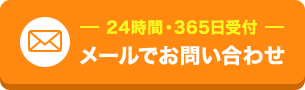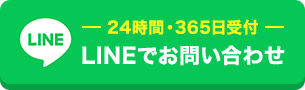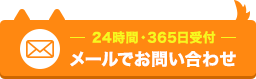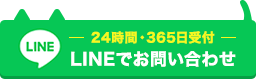ペットちゃんの遺骨の分骨を希望していても「分骨するのは良くないのではないか」と心配になる方も多いです。
そこで今回は、分骨について飼い主様が抱えている疑問や不安を解決し、ペットちゃんを慈しみながら手元で供養する方法についてご説明いたします。
この記事の監修者

高間 健太郎
(獣医師)
大阪府立大学農学部獣医学科を卒業後、動物病院に勤務。診察の際は「自分が飼っている動物ならどうするか」を基準に、飼い主と動物の気持ちに寄り添って判断するのがモットー。経験と知識に基づいた情報を発信し、ペットに関するお困り事の解消を目指します。
ペットの分骨は良くない?

「分骨」とは文字通りご遺骨を複数に分けて供養することです。
最近では飼い主様やご家族様の思いに沿った方法で分骨をしてペットちゃんを供養する方も増えています。
①分骨をする目的
ご家族と離れて暮らしている場合にそれぞれのお宅でペットちゃんを供養したいという場合や、ペットちゃんと離れたくないという思いでご遺骨の一部を手元に置いていたい場合に選ばれている供養方法です。
リビングなどに置いてこれまでと同じようにペットちゃんと一緒に暮らす、ご自身が通いやすい霊園に埋葬するなど、分骨した遺骨は飼い主様の意向に沿って供養することができます。
②分骨すると成仏できない?
「分骨するとあの世で五体満足でいられず、魂まで分割されて成仏できない」という風潮を心配する声もよく耳にします。しかし、分骨は仏教やキリスト教においても古来から行われていた供養方法です。遺骨自体に魂が宿っているのではなく「遺骨を生きた証として供養する」という考え方で選ばれている供養方法と言えます。
自分が生きた証であるご遺骨を分骨してご家族の皆様で供養してもらえればペットちゃんもきっと喜んでくれるでしょうし、ご家族様もペットちゃんを身近に感じながら心穏やかに供養できるはずです。供養を心の拠り所とすることは決して悪いことではありません。むしろ尊い行いですので、分骨を希望する方はどうかご安心ください。
分骨はいつするのか

分骨は下記のタイミングで行われることが多いようです。
- 火葬後の骨壺に収める前
- 四十九日などの節目
- お盆などで家族が集まったとき
- 散骨をする前
- お墓や納骨堂に収められている遺骨を取り出したとき
基本的に分骨は必要なときにいつでもできますが、合同供養塔へ納骨した場合や、土中への埋葬や散骨をしてしまうと分骨はできませんので、後悔しないように事前に家族で相談しておきましょう。
分骨は火葬後の拾骨の際にしておくのがベスト
一度骨壺に納骨してしまうと分骨は困難になるので、分骨を希望する場合は拾骨の時点で行っておくのがベストですが、火葬はペットちゃんが亡くなった後すぐに行う必要があるため、気持ちの整理を行うための十分な時間が確保できず、分骨用の骨壺や容器を事前に揃えるのが困難な場合があります。
容器の用意が間に合わない場合は、拾骨前にチャック付きの小さなポリ袋を準備して、一時的に保管する簡易的な分骨を行うのもおすすめです。そうすれば、準備が出来次第いつでも分骨することができます。
分骨する骨はどこがいい?

仏教では「再生する骨」である歯や爪を分骨するのが良いとされています。
しかし、ペットちゃんの身体の大きさや火葬の状況によっては全ての骨がきれいに残るとは限りません。どこの骨でも分骨用に選べますので、歯や爪にこだわらず、火葬後にきれいな形で残っている骨を分骨するようにしましょう。
①思い出深い部位を選ぶ
ペットちゃんを身近に感じられるように「よく引っ掻かれた」という方は爪で「尻尾が可愛かった」という場合は尻尾の骨のように、思い出深い部位の骨を選ぶ方も多いです。
また、骨と一緒に羽や毛の一部を保管するのもおすすめです。
筆者が飼っていた犬が亡くなったのは10年ほど前ですが、今でも温かく柔らかな毛並みが恋しくなることがあります。家族としての絆は生涯残るもの。どうしても寂しくなった時のために、毛並みや思い出深い部位を残しておくことは、とても大切だと思います。残す部位は慎重に選びましょう。
②分骨する骨壺や容器の大きさで選ぶ
分骨したご遺骨を納める容器によって、拾骨の量や大きさは変わります。
歯や爪数個で十分な場合もあれば、ある程度大きい容器の場合はそれに見合った量のご遺骨を納める場合もあります。
*ご遺骨は絶対に手で触らない!
手の脂やタンパク質がご遺骨に付着してしまうと、そこからカビが繁殖することがあるため、ご自身で分骨をするときは、必ず手袋をつけるか、お箸を使ってください。
分骨後の入れ物の種類と選び方

ペットちゃんのご遺骨を自宅などに保管して供養する「手元供養」も人気です。アクセサリーやペンダントにして持ち歩くなど、ライフスタイルにあわせた方法を選べるのも魅力です。
手元供養を行うためには仏具店やメモリアルグッズ専門店で取り扱っている専用容器から雑貨店などで購入できる木製の小箱や小さな瓶まで様々な容器がありますが、分骨すれば長期間にわたって保管したり、持ち運んだりする必要があるため、下記のポイントをしっかりと押さえて容器を選ぶようにしましょう。
- 湿気が入らないこと
- 錆びないこと
- 持ち運びしやすいこと
- ある程度の強度があること
現在では「分骨用」の容器も数多く販売されており、ご遺骨を保管するための綿や小袋が付属していたり密封できたりするものもあります。用途や希望に合わせて選びやすいので、以下のように専用の容器を用意するのがおすすめです。
①分骨用骨壺
大きさや形だけではなく、デザインも部屋に溶け込むスタイリッシュなものから可愛らしいものまで様々な骨壺があります。中には亡くなったペットちゃんの写真をもとに外見がそっくりな陶器製の骨壺をオーダーメイドで製作してくれる仏具店やメモリアルグッズを扱う会社も存在しています。金属製やガラス製など、素材へのこだわりが多いのも骨壺の特徴です。
②分骨用カプセル
歯や爪などのご遺骨を納める場合に適しているのがカプセルです。色やデザインも豊富で5㎝程度と非常にコンパクトなので、ストラップやネックレスとして肌身離さず持ち歩いたり、ペットちゃん似のぬいぐるみに付けたりすることができます。また、ペットちゃんの名前や命日が刻印できるものもあり、ご家族様にとても好評です。
③分骨用ネックレス・ペンダント
ネックレスやペンダントの中に分骨したご遺骨を粉骨して納める方法です。心の拠り所としてペットちゃんをいつもそばに感じることができるため、ネックレスやペンダントなどのアクセサリーにして供養している方も数多くいらっしゃいます。
ペットちゃんの分骨は自分でできる?

家族との話し合いの結果やご自身の心境の変化などで、ペットちゃんのお骨を分骨したくなった場合、自力で分骨を行うことはできるのでしょうか?
自力での分骨は可能
人間の場合は火葬場や自治体に分骨を行うことを申請して「分骨証明書」を発行してもらうことが法律で義務付けられていますが、ペットちゃんの場合はこうした証明書は不要です。 ただし、お骨がある場所によって対応が異なるため、分骨する際は注意しましょう。
手元供養
お家など手元にお骨がある場合は、そのまま分骨を行って問題ありません。
埋葬後
ペットちゃんを埋葬する場合は「ご自宅の庭などの私有地に埋葬」「霊園に埋葬」「樹木葬」などの選択肢があります。しかし、基本的には埋葬後に分骨を行うことはおすすめできません。
お骨をお庭に埋葬した場合は場所さえわかっていれば掘り起こすことはできますが、土で汚れてしまっている場合が多く、霊園や管理された場所での樹木葬を行っている場合は基本的に一度埋葬したお骨を返してもらうことはできないためです。
自分で分骨する方法
分骨を行う入れ物を用意したら、骨壺を開けてお骨を入れていきます。
お骨は崩れやすいため、触るときはあまり力を入れず、カビ防止のために直接触れないように注意しましょう。
分骨後を考える
「全国石製品協同組合」が全国の40代から60代の男性・女性613名を対象に行った「老後のお墓についての心配事」というアンケートでは「お墓を維持すること」が最も多い割合を占めており、お墓を所有しており、継承者がいない場合は「お墓をしまうこと」が心配だと答えた方が多数存在しました。
これは人間の場合のアンケートではありますが、霊園に埋葬した場合は定期的なお参りや管理が必要になり、ペットちゃんのお墓は相続税の課税対象になるなど、大切な家族に負担を掛けないように、分骨後のお骨の管理はペットちゃんの場合でもよく考えておく必要があります。
ライフスタイルにあわせて供養できるようになるのが分骨を行うメリットではありますが、いつかご自身でのお骨の管理が難しくなった時のために永代供養を依頼できる近場の霊園を調べておくなど、これからのことを考えておくことも大切です。
永代供養について詳しく知りたい方は、以下のコラムを参考にしてください。
※参考サイト
「老後のお墓についての心配事」についてのアンケート調査 全石協
まとめ
分骨は決して悪いことではなく、むしろ、尊い行いとして古くから習慣となっている供養方法です。ご家族様が生前同様に愛情深くペットちゃんを思って供養してあげれば、ペットちゃんも安らかな気持ちで眠れるはずです。
分骨の方法もご家族様の思いやライフスタイルに合わせて様々な方法を選べます。骨壺に入れてペットちゃんの写真と一緒に飾る、遺骨をネックレスやペンダントの中に納めるなど、ペットちゃんとご家族様の双方にとって最善となる供養方法を選び、いつまでもペットちゃんを慈しんであげてください。