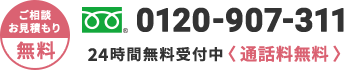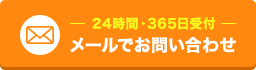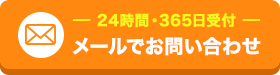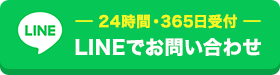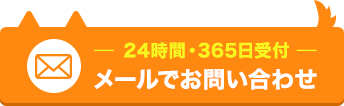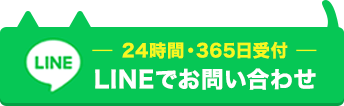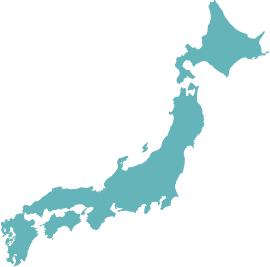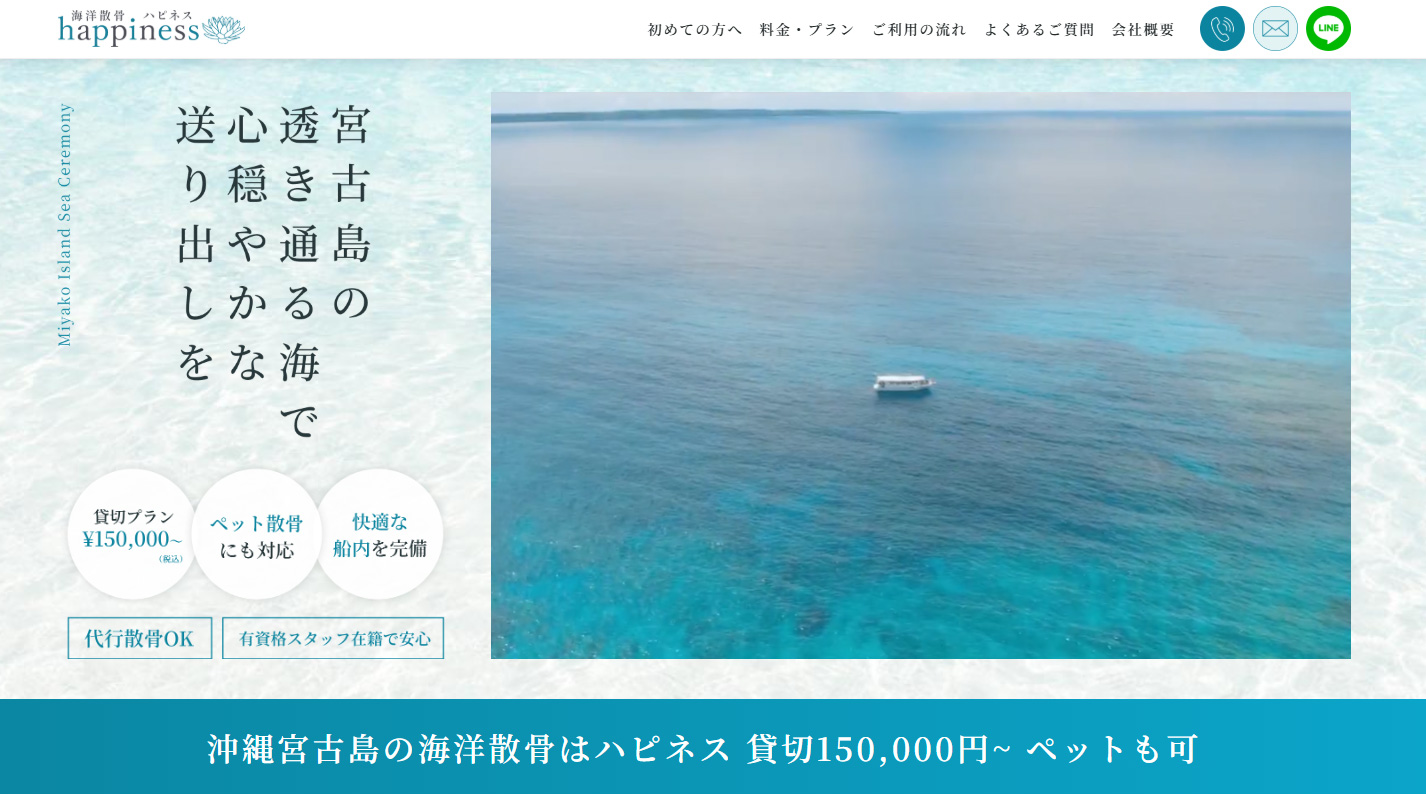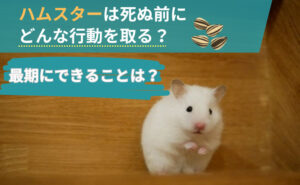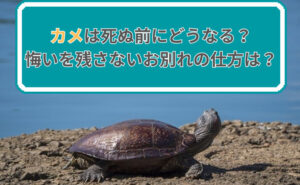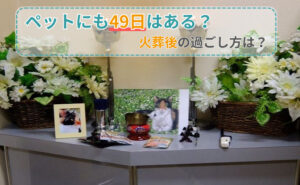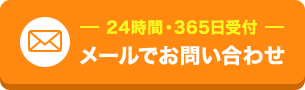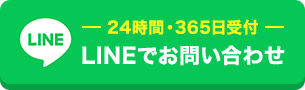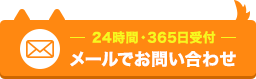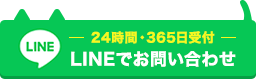たくさんの愛情を注いできた愛犬を失うと、まるで自分の一部が欠けてしまったような感覚に陥る飼い主様もおられるでしょう。
とくに小型犬は、飼い主様にべったりとなつくことも多いため、そのぬくもりがなくなることで非常に大きな喪失感をもらたします。
しかし、つらいからと言って最後まで満足にお世話ができず、丁寧に見送ってあげられなかったら、きっとずっと後悔が残るはずです。
後悔は、ペットロスを悪化させ心身に不調をきたす可能性もあるので、悔いを残さないように、できることは全部してあげるようにしましょう。
当記事では、充実したお見送りをするための準備や供養方法、死後の手続きなど、小型犬を亡くした際に必要になることを、順を追ってわかりやすく解説いたします。
●小型犬の遺体のエンゼルケア(保清処置)と安置を行う
エンゼルケアは「ペットちゃんの尊厳を守る」「飼い主様の心のケア」「衛生的に保つ」、そして安置は「火葬まできれいな姿を保つ」ために行います
●小型犬の火葬方法と遺骨の供養方法を決める
火葬方法は3種類、供養方法は4種類から選びます
●小型犬の死後の手続きを行う
行政への届け出、マイクロチップ登録機関への申請などを行います
これらを一つひとつペットちゃんを想いながら行うことで、飼い主様の心も少しずつ整理していけるのではないでしょうか。
とはいえ、それでも悲しみや寂しさがが消えてなくなるわけではありません。
そこで、ペットロスの重症化を防ぎ、悲しみを乗り越えるためのアプローチ方法についてもご紹介いたしますので、ご参考くださいませ。
小型犬が亡くなったら心を込めてエンゼルケア(保清処置)をしよう

エンゼルケアは、小型犬の体を清潔に整えてあげることで、ペットちゃんの尊厳を守り、いつも通りの可愛らしい姿にしてあげる処置です。
丁寧にエンゼルケアを行うことで、飼い主様の心を慰めることにもつながります。
加えて、ご家族や他のペットちゃんへの感染症予防の側面もありますので、以下の手順を参考に行ってください。
①エンゼルケアに必要なものを準備する
ペットちゃんの体を清潔にするために以下のものを用意してください。
・濡らして絞ったタオルやウェットティッシュ
・バスタオルや毛布、ペットシーツ
・綿球や脱脂綿、ティッシュ
・毛並ブラシ

②小型犬を寝ているような楽な体勢に整える
バスタオルや毛布、ペットシーツを敷いた上にペットちゃんを寝かせます。
このとき、手足を体に寄せて、丸まって眠っているような体勢に整えてあげましょう。

目が開いている場合は、手のひらでなでるようにして優しく閉じ、口が開いている場合は舌をしまうようにして閉じてあげましょう。
小型犬は死後1時間~1時間半ほどで死後硬直が始まります
小型犬は骨も小さく細いので、硬直した状態で無理に体勢を変えようとすると骨折してしまうことがあるので注意してください
硬直してしまうと24時間ほど経過して解硬(かいこう:再び柔らかくなる)するまで体勢を変えられなくなるため、できれば死後硬直が始まる前にエンゼルケアを行いましょう
③小型犬の体を拭き清潔にする
濡らしてよく絞ったタオルやウェットティッシュで、ペットちゃんの体を隅々まで拭いてきれいにしてあげましょう。
とくに目や口周り、耳、お尻などは汚れやすい箇所なので、丁寧に拭くようにします。

遺体からは体液や排泄物が漏れてしまうことがあるため、お尻や鼻には綿球や脱脂綿を詰めてあげてください。
遺体が濡れたままだと傷みの原因になるため、濡れすぎてしまった場合は乾いたタオルで再度拭いてあげましょう
④小型犬をブラッシングして毛並を整える
仕上げに、ペットちゃんの全身を優しくブラッシングして毛並を整えます。

小型犬の遺体を棺に納めて冷やし、冷暗所に安置する

小型犬の遺体は、体内の細菌が細胞を分解していくことで徐々に腐敗してしまいます。
ペットちゃんを生前と同様のきれいな姿で送り出してあげられるように、適切な方法で遺体を冷却・安置しましょう。
ここでご紹介する方法を実践すれば、夏場で1~2日ほど、冬場で2~3日ほどきれいな姿を保てます。
①安置に必要なものを準備する
まずはペットちゃんの棺や、遺体の冷却に必要なものを用意しましょう。
・ペットちゃんの体が余裕をもって納まる大きさの箱(ダンボール箱やペット用棺)
・バスタオル、タオル
・ペットシーツ
・保冷剤、ドライアイスなど

②棺を整えて中に小型犬を寝かせる
棺となる箱の中にはペットシーツを敷き、その上にバスタオルやタオルを敷きます。
棺が整えられたら、その中にペットちゃんを寝かせてあげましょう。

③保冷剤を布で包み小型犬の周りに置いて冷やす
保冷剤やドライアイスはタオルなどで包み、ペットちゃんの体の周りに配置しましょう。
とくに傷みやすい腹部や頭部は重点的に冷やしてください。

・保冷剤は溶け切る前に新しいものに交換してください
・ドライアイスを使用する場合は軍手などを使用し、素手では触れないでください
・ドライアイスを使用する場合は、部屋を換気し、棺も密封しないようにしてください
④小型犬の棺を冷暗所に安置する
夏場なら冷房の効いた部屋、冬場なら煖房を入れていない部屋を選び、棺を安置してください。
日光やエアコンの風が遺体に当たらないように注意し、火葬までの間、ペットちゃんを静かに眠らせてあげましょう。

ペットちゃんが生前好きだったおやつやおもちゃ、供花などをお供えしてあげるのもおすすめです。
小型犬とのお別れの準備|火葬方法を選び手配する

小型犬の火葬は「自治体」「訪問ペット火葬業者」「ペット霊園」の3か所に依頼することができます。
それぞれのメリット・デメリットを解説し、どんな飼い主様におすすめなのかをお伝えしますので、参考にしてください。
火葬方法が決まれば、実際に問い合わせて火葬の手配を行いましょう。
【自治体】は安価で火葬できるが拾骨・返骨はできない
| こんな飼い主様におすすめ | メリット | デメリット |
| ・費用をできるだけ抑えたい ・供養方法にはこだわらない | ・安価で火葬できる ・行政対応なので安心できる | ・火葬の日時を選べない ・火葬に立ち会えない ・遺骨の拾骨や返骨はできない ・遺骨、遺灰は一般ゴミと一緒に埋め立てられる ・供養方法が選べない |
自治体では、ペットちゃんの遺体を引き取り火葬を行ってくれます。
地域によって費用はまちまちですが概ね数千円程度で依頼できるようです。
ただし、自治体ではペットちゃんの遺体を一般廃棄物として扱うため、他の動物たちと一緒に、または廃棄物と一緒に焼却するのが基本です。
高火力での焼却になるため遺骨は残らず、遺灰は埋め立て地へと運ばれることになります。
「費用を抑えたい」「供養方法にはこだわらない」という飼い主様には良いのですが、「遺骨を返却してほしい」「遺骨は霊園へ埋葬したい」とお考えの飼い主様にはおすすめできません。
中には例外的に、個別火葬や返骨に対応してくれたり、遺骨を共同墓地に埋葬してくれたりする自治体もありますので、詳しくはお住まいの自治体のホームページをご確認ください。
ペットちゃんの火葬については、自治体ごとの対応が大きく異なります。
後から悔やむことがないように、利用する前にはどのような対応になるか、しっかりと確認しておきましょう。
戸塚斎場での火葬の場合、事前申込でお骨の持ち帰りや個別の火葬に対応可能
戸塚斎場:045‐864‐7001
| 個別火葬 | 1㎏未満:10,000円 1㎏以上5㎏未満:20,000円 5㎏以上25㎏未満:25,000円 |
大宮聖苑に依頼すれば個別火葬や遺骨の返却に応じてもらえる
大宮聖苑:048‐682‐2800
| 個別火葬 | 15㎏未満:8,380円 |
下記聖苑へ問い合わせた際に収骨したい旨を伝えて予約すれば対応可能
志賀聖苑:077‐592‐2000
大津聖苑:077‐534‐4400(令和7年5月1日から令和7年10月31日までは火葬業務を一時休止)
| 収骨する場合 | 市民8,800円/他市民22,800円 5㎏以上15㎏未満:市民11,000円/他市民28,600円 |
【訪問ペット火葬業者】は好きな場所で自分らしい葬儀ができる
| こんな飼い主様におすすめ | メリット | デメリット |
| ・外出が難しい ・家族みんなで見送ってあげたい ・丁寧な葬儀、供養がしたい | ・火葬の日時を指定できる ・慣れ親しんだ場所や思い出の場所で見送れる ・家族みんなで見送れる ・拾骨や返骨が可能 ・丁寧な葬儀ができる ・遺骨の供養方法が選べる | ・費用がやや高額になる ・慎重に業者選びをする必要がある |
多忙なうえに車を持たない方も多い現代人のライフスタイルにマッチしたペットちゃんの火葬方法として注目されているのが訪問ペット火葬業者です。
ペット用火葬炉を搭載した車で飼い主様の自宅や指定の場所まで来て、その場で火葬を行ってくれるため利用しやすいのが特徴です。
思い出の場所でペット仲間にも列席してもらうなど、自由なお見送りができます。
また遺骨の拾骨や返骨にも対応できるので、「自分の手でお骨を拾ってあげたい」「遺骨は自宅に連れ帰って供養したい」という飼い主様にもおすすめです。
料金は自治体と比べるとやや高く、ペット霊園よりは安い価格帯になります。
火葬方法は「合同火葬」「一任個別火葬」「立会個別火葬」の3種類から選べるところが多いです。
合同火葬……他のペットちゃんと一緒に火葬するため、遺骨の返骨はできない。
一任個別火葬……ペットちゃんだけを個別に火葬する。スタッフが拾骨を行う。希望すれば返骨が可能。
立会個別火葬……ペットちゃんだけを個別に火葬する。飼い主様の手で拾骨できる。返骨も可能。
*ペット火葬ハピネスでは、飼い主様宅で葬儀を執り行い、その後火葬車で火葬するという丁寧な葬儀ができる「自宅セレモニー葬」もご用意しています。

注意点としては、悪質な業者に騙されないようにすることです。
ほとんどの業者は、飼い主様やペットちゃんのために誠実に火葬を行っていますが、中には悪質な業者も紛れており、ペットちゃんの遺体を不法投棄されるなどの被害も出ています。
そんな悲しい思いをしないように、できれば3社程度で比較検討して優良な業者を見つけるようにしましょう。
【ペット霊園】は人と同じような丁寧な葬儀ができる
| こんな飼い主様におすすめ | メリット | デメリット |
| ・人と同じような葬儀がしたい ・遺骨をそのまま霊園に納骨・埋葬したい | ・火葬の日時を指定できる ・天候に左右されない ・丁寧な葬儀ができる ・拾骨や返骨が可能 ・遺骨の供養方法が選べる | ・費用が高額になる ・アクセスしにくい郊外にあることが多い |
人の葬儀さながらのセレモニーを行い、その後火葬から墓地への埋葬までを一連の流れでできるのがペット霊園の特徴です。
墓地の管理はもちろん、年忌法要や供養祭を行っているところも多いので、お任せすれば丁寧な供養ができます。
墓地への埋葬時以外は室内で行われるため、天候の影響を受けないのも嬉しいポイントです。
しかし、広い敷地が必要になる関係でペット霊園は郊外にあることが多く、アクセスしにくい点は考慮しておかなくてはいけません。
また、施設利用料も含めた料金になっているため、3つの火葬方法の中では一番高額になります。
「人と同じように手厚く供養してあげたい」「遺骨の納骨・埋葬までお願いしたい」という飼い主様におすすめです。
小型犬の供養方法を決める|手元供養・自宅埋葬・霊園への納骨・自然散骨

火葬を終えたペットちゃんの遺骨をどのように供養するかは、「飼い主様の想い」と「掛かる費用」そして「遺骨の管理の難易度」を総合的に考えて決めましょう。
代表的な4つの供養方法をご紹介しますので、ペットちゃんの安らかな眠りを祈り、飼い主様の心の癒しになるであろう方法を選んでくださいね。
【手元供養】ならいつでもペットちゃんと一緒にいられる
手元供養とは、ペットちゃんの遺骨を身近な場所に保管して供養する方法のことで、自宅に祭壇を作り遺骨を祀る方法と、アクセサリーやキーホルダーにして身につける方法があります。
小型犬の場合、骨壺も小さなもの(直径10㎝×高さ12㎝ほど)になるので場所を取らず、またインテリアに違和感なくなじむ飾りやすいデザインのものも多数販売されています。
最近では、骨壺がちょうど納まるメモリアルボックスやペット用の仏具セットなどもありますし、遺骨が納められるペンダントの他、遺骨自体を加工して合成ダイヤモンドなどを作ることもできます。
ペットちゃんが寂しがり屋な子だった場合や、ペットちゃんといつも一緒にいたい飼い主様にぴったりな方法でしょう。
【自宅埋葬】はいつでもお墓参りできる
ペットちゃんの遺骨は、公有地への埋葬は法律で禁止されていますが、私有地やプランターであれば問題ありません。
いつでもお墓に手を合わせることができる環境は、心の平穏を取り戻すのにも有効でしょう。
墓標代わりに植物を植えれば、ペットちゃんと過ごした日々のように、毎日のお世話をすることもできます。
ただし、明らかにお墓とわかるようなものを、近隣の方の目につく場所に作るのはおすすめできません。
飼い主様にとっては愛するペットちゃんでも、他の方にとってはそうではなく、中には嫌な思いをされる方もおられるかもしれないからです。
また、私有地に埋葬した場合は、遺骨が土に還るまでの十数年間は、気軽に引越しや土地の売却ができなくなることも覚えておきましょう。
【ペット霊園への納骨・埋葬】は丁寧な供養ができる
ペット霊園は、ペットちゃんの火葬から供養までを行うために作られた施設で、墓地(合同・個別)や納骨堂(霊座)の他、樹木葬や飼い主様と入れるお墓を提供しているところもあります。
定期的に法要や供養祭が執り行われ、丁寧な供養が受けられます。
ペット霊園はアクセスしにくい場所にあることが多く、頻繁にお墓参りをするのは難しいかもしれませんが、その分、普段のお墓の管理は任せることができます。
「忙しくて自分では遺骨の管理が難しいが、しっかりと供養してあげたい」という飼い主様におすすめの方法です。
筆者も歴代のペットちゃんたちをこの方法で供養しており、ペット霊園からは毎年年忌法要のお知らせがきちんと届きます。
お墓参りに訪れると、きれいに整備された墓地と自然豊かな環境に心が癒されるように感じます。
【自然散骨】はお出掛け好きだった子におすすめ
お墓を持たず、大自然にペットちゃんを託す方法として自然散骨を選ばれる飼い主様もおられます。
「お出掛け好きだったペットちゃんのために」「あの子は海(山)が好きだったから」などの理由から選ばれているようです。
散骨を行うためには、遺骨を粉骨(パウダー状)する必要がありますし、私有地や許可を得た場所で行う、周囲への配慮をするなど気を付けなければいけないことも多いので注意しましょう。
また、手元に遺骨が残らないので、後悔しないように十分考えてから行ってください。
小型犬の火葬・供養後にすべきこと|死亡届・各種手続き

小型犬の火葬や供養が無事に終わっても、飼い主様にはまだしなくてはいけないことがあります。
それは死亡届の提出やマイクロチップ登録機関へ死亡申請などの手続きです。
ここでは、忘れてはいけない手続きについて詳しくご紹介します。
小型犬が亡くなった日から30日以内に死亡届を提出する
飼い犬が亡くなった際には、死後30日以内にお住まいの市町村へ死亡届を提出することが法律*により義務付けられています。
期限を過ぎると20万円以下の罰金刑を受ける可能もあるので気をつけてください。
小型犬の死後30日以内にマイクロチップ登録機関へ死亡申請を行う
ペットちゃんがマイクロチップを装着している場合は、登録機関への死亡申請も必要です。
こちらも死後30日以内に行いましょう。
自治体によっては、マイクロチップ登録機関へ死亡申請を行うことで、同時に自治体への申請が完了する特例措置を行っているところもあります。
対応できる自治体はまだまだ限られているため、詳しくはお住まいの自治体に問い合わせるかホームページなどを確認してください
ペット保険に加入している場合は小型犬の死亡を届け出る
ペット保険に加入していた場合は、保険の失効手続きを行いましょう。
ペットちゃんの死亡した日を証明できる「死亡診断書」や「火葬証明書」を用意しておくとスムーズです。
また、未請求の診療費がないかも確認しておきましょう。
ペット保険の特約で、火葬・葬儀費用や供養の費用を一部補償してくれるものもあるので、特約を付けている場合はこちらも忘れずに申請してください。
血統書団体に所属している場合は血統書を返還する
ペットちゃんが血統書団体に所属しているなら、血統書を返還して登録の抹消手続きを行いましょう。
手続きの方法は団体によっても異なるので、まずは電話やメールでペットちゃんが亡くなったことを伝え、手続き方法を確認してください。
ペットちゃんの死亡を証明する「死亡診断書」や「火葬証明書」の提出を求められることもあるようです。
血統書は返還するものですが、ペットちゃんとの思い出の一つとして手元に残したい場合は、団体へ気持ちを伝えて相談するか、コピーしたものを記念に残すようにしましょう。
悲しみを乗り越えるための手順|ペットロスとの向き合い方

個体差はありますが、小型犬は好奇心旺盛で活発、意外と気が強い半面、甘えん坊という性格の子が多いそうです。
飼い主様に信頼を寄せてべったりになっている子もよく見かけます。
その分、甘えてくれる存在がいなくなってしまったという喪失感は想像以上に大きく、程度の差はあれどペットロスに陥る飼い主様も少なくありません。
重症化すると食欲不振や睡眠障害、憂鬱感、だるさ、無気力感、めまい、情緒不安定、幻覚、幻聴など、様々な症状が現れます。
しかし、飼い主様が亡き愛犬に囚われ続けるのではなく、「前を向いて笑って生きて行ってほしいと」ペットちゃんは望んでいるのではないでしょうか。
ここでは、悲しみを乗り越え、ペットロスとどう向き合っていくと良いのかにスポットを当てて解説いたします。
しっかりと供養する
まずはペットちゃんをしっかりと供養してあげましょう。
火葬方法や供養方法は、安さや手軽さだけで選ぶのではなく、「ペットちゃんを大切に扱ってもらえるか」「後々後悔しないか」を十分に考慮して選んでください。
悲しい、つらい気持ちを無理に抑えない
悲しみ、怒り、罪悪感などの感情は無理に抑え込まないようにしましょう。
悲しい時には思いっきり泣き、つらい気持ちは誰かに話したり、紙に書き出したりして表現するようにします。
感情の抑制は心身に悪影響を及ぼし、うつ病などの精神疾患の発症リスクを高めてしまいます。
家族や同じ経験をした人と想いを分かち合う
愛するペットとの別れを経験したことがある人と話すことで、「自分だけじゃない」という事実に心が軽くなるように感じられるでしょう。
悲しみや不安な想いは人と分かち合うことで軽減できるのです。
ペットちゃんを身近に感じられるようにする
ペットちゃんの写真を飾る、遺骨を入れたメモリアルボックスを用意する、遺骨アクセサリーを身につける、などペットちゃんの存在を身近に感じられるようにするのも良い方法です。
「姿は見えなくなっても、近くにずっといてくれる」と感じられ、安心感を得られます。
ペットちゃんの遺品整理をする
少し気持ちが落ち着いてきたら、ペットちゃんの遺品整理をするのもおすすめです。
すべてを処分する必要はありませんので、形見として残したいもの以外を少しずつ整理していきましょう。
捨てることに抵抗を感じる場合は、ボランティアに寄付するのはいかがでしょうか。
ペットちゃん用に買っていたおやつや玩具、洋服、ペット用品などを、ペット同伴被災者へ届けるボランティアなども行われています。
趣味や好きなことに打ち込む
音楽鑑賞、映画鑑賞、読書など、自分の好きなことに没頭することで、一時的にペットちゃんを亡くした悲しみを忘れることができます。
悲しみから離れる時間を作ることで、心を休め、回復を促すことが期待できます。
運動を始める
身体を動かすことは気分転換やストレス発散につながります。
散歩やジョギング、ヨガなど、心地良い疲労感を感じる程度の運動がおすすめです。
運動後はぬるめのお風呂にゆっくりと浸かれば、疲労感とリラックス効果で睡眠の質も向上すると言われています。
専門家のサポートを受ける
周囲に話せる人がいない、なかなかペットロスの症状が改善しない、というときは専門家のサポートを受けましょう。
ペットロスカウンセラーは、カウンセリングを通じて飼い主様の悲しみに寄り添い、心の整理や回復を助けてくれます。
抑うつ症状や不眠、幻覚といった精神的・身体的な症状が重い飼い主様は、心療内科や精神科を受診し、適切な治療を受けましょう。
筆者も小型犬との別れを3度経験しています。
母にべったりだった子が亡くなったときには、母が重いペットロスに陥ってしまいました。
気力を失くし、毎日のように涙を流してご飯も食べずにいたため、私も心配でたくさん話しを聞くようにしていました。
そんなある日、父が子犬を連れて帰って来たのですが、その子のお世話を始めた途端、母はみるみる元気になっていきました。
いなくなった子の代わりとして新しいペットを迎えるというのは、前の子と比べてしまう可能性もあるため注意が必要です。
母の場合は、良い方向に進んだので良かったのですが、個人的には、亡くした子への想いが整理でき、新しい子を迎えたいという気持ちが芽生えてからが最善のタイミングではないかと思っています。
ペットロスからの回復に、何が効果的か、どれくらいの時間がかかるかは、人によっても様々です。
少しずつで良いので、ペットちゃんとの別れを受け入れられるように、ご紹介した方法を試してみてください。
まとめ
小型犬は、身体が小さいので、大型犬や中型犬に比べて死後硬直が早く始まってしまいます。
悲しい別れを迎えて間もない中で、飼い主様には大変なことですが、ペットちゃんをきれいな姿で送り出してあげられるように、できるだけ早くエンゼルケア(遺体の保清処置)と安置をしてあげましょう。
そして、ペットちゃんが安心して旅立てるように、また飼い主様自身の心の整理ができるように、納得の火葬・葬儀をしてあげて欲しいと思います。
ハピネスでは、「ペットちゃんらしいあたたかな葬儀をしてあげたい」「火葬後の供養方法まで相談したい」という飼い主様のご相談を承っております。
24時間お電話を受け付けておりますので、気兼ねなくお問い合わせください。
この記事の執筆者

ペット火葬
ハピネス 編集部 S・A
愛犬・愛猫・愛鳥など8匹以上を見送った経験を持ち、現在も愛犬と暮らす動物愛好家。初代愛犬を満足に供養できなかった経験からペット火葬ハピネスへ入社。あたたかなペット葬儀のための情報を発信。私生活では動物保護ボランティアへの支援を行っている。