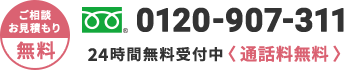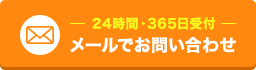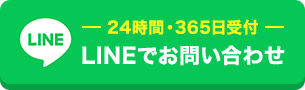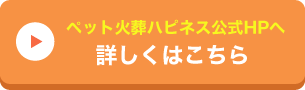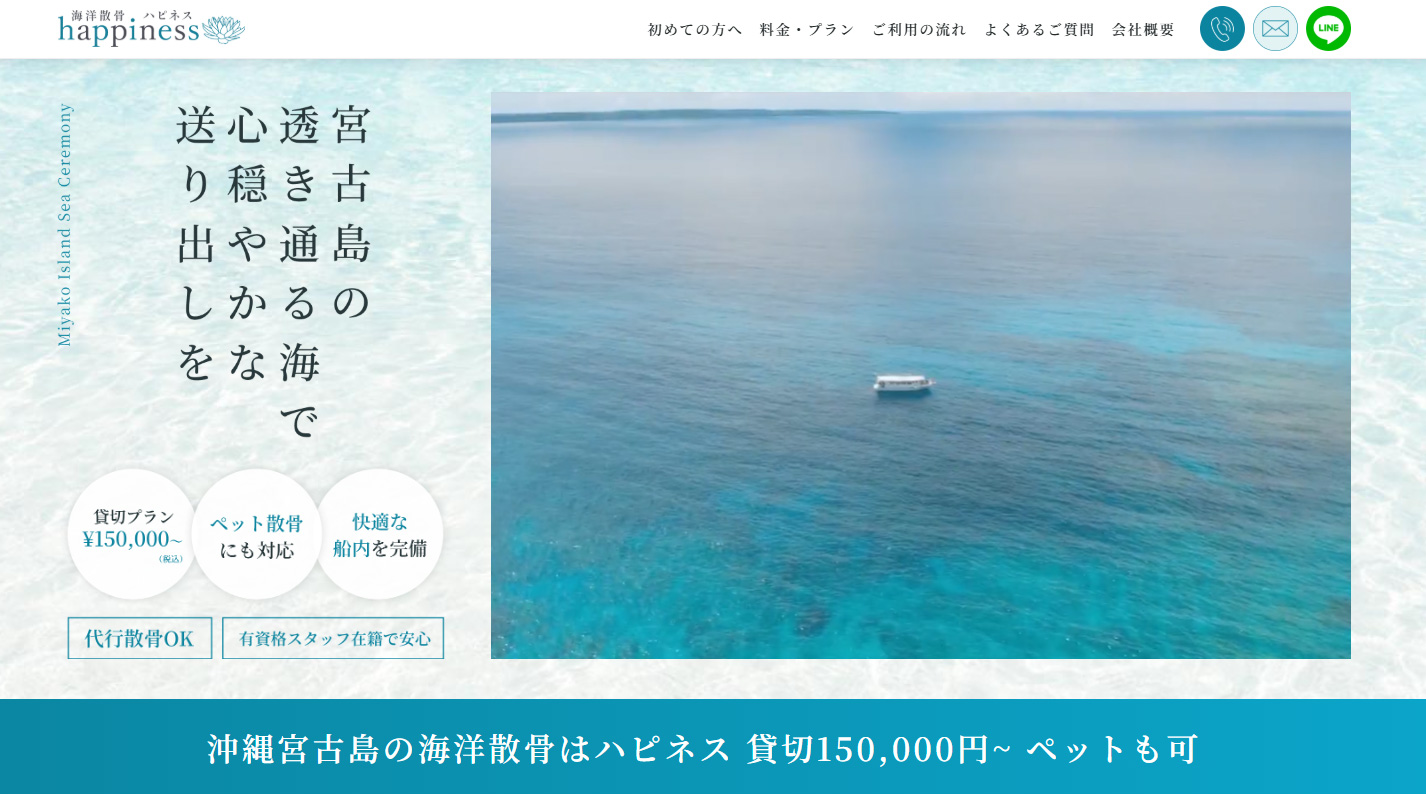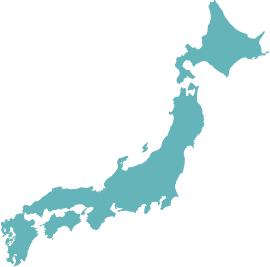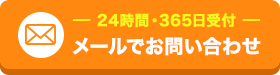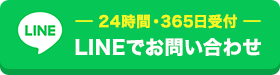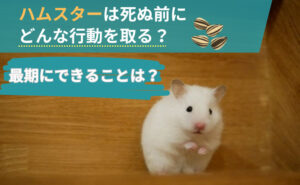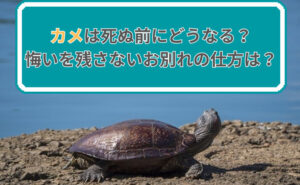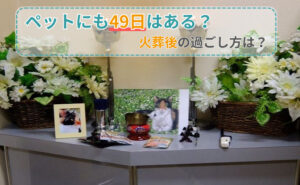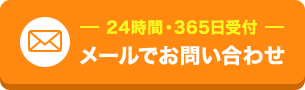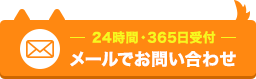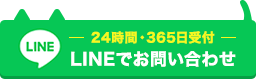フトアゴヒゲトカゲは、恐竜のような格好良い見た目に反して、性格は穏やかで人にも慣れやすい子が多く、ペットとしてとても人気です。
また、昼行性なので飼いやすいという特徴もあります。
しかし、幼体である生後3カ月頃までは免疫力が低く、少しの環境変化やストレスから急変して突然死してしまうことがあり「魔の3カ月」と呼ばれているのです。
幼体の飼育は上級者向けのため、初めて飼う人にはある程度成長したヤング~アダルトの個体がおすすめされています。
平均寿命は8~12年ほどで、中には15年以上もの長生きをする子もいるようです。

今現在、フトアゴヒゲトカゲちゃんと一緒に暮らしておられる飼い主様は、我が子に元気で長生きしてもらいたいと願っておられるでしょう。
それを叶えるためには、病気やケガの予防が一番大切ですが、体調不良や死の予兆にいち早く気付き対処することも同じくらい大切です。
フトアゴヒゲトカゲが亡くなる前には以下のような症状が見られることがあります。
・体色が黒くなり色が戻らない
・ご飯を食べない(体重の減少)
・水を飲まない
・目を閉じたまま動かない
・呼吸が乱れる
そして、フトアゴヒゲトカゲちゃんとの生活で、とくに注意すべきは冬眠状態と死亡を見間違わないようにすることです。
フトアゴヒゲトカゲはブルーメーションと呼ばれる軽い冬眠状態になることや、ストレスなどが原因で仮死状態に陥ることがあります。
これを死亡していると勘違いしてしまうと大変です。
判断を誤って悲しい別れにならないように、当記事では「仮死状態と死亡の見分け方」を含めた次の4つの備えを解説します。
・亡くなる前に現れる症状を知り、その原因と対策を行う
・仮死状態と死亡の見分け方、仮死状態からの起こし方を確認する
・死亡時のエンゼルケア(遺体の保清処置)と安置方法を確認する
・火葬の依頼先や供養方法を選んでおく
いざ、その時が来てからでは慌ててしまい、後悔することにもなりかねません。
気持ちに余裕のある今の内から終末期やお見送りへの備えを始めましょう。
フトアゴヒゲトカゲが亡くなる前はどんな異変が現れる?原因と対策

フトアゴヒゲトカゲは、本能的に弱っている姿を周りに悟られないように隠そうとします。
そのため、「様子がおかしい」と飼い主様が感じたすぐ後に容態が急変して亡くなってしまうこともあるのです。
少しでも早くペットちゃんの異変に気付けるように、毎日しっかりと様子を観察しておきましょう。
また、何かあった時のために爬虫類を診察できる動物病院を見つけておくと共に、年に1~2回を目安に定期検診を受けておくことも推奨します。
ここでは、フトアゴヒゲトカゲが亡くなる前に見られる異変と、その原因と対策をご紹介します。
体色が黒くなり色が戻らない
フトアゴヒゲトカゲは、ストレスを感じるとメラニン色素が過剰に生成され、喉元からお腹にかけてストレスマークと呼ばれる黒い模様が現れます。
他にもオスの場合は、発情期に求愛行動として喉を黒くすることが知られていますし、威嚇行動として喉を黒くすることもあるようです。
また、脱皮前にも全身がやや黒っぽくなることがあります。

一時的なものであれば問題ないのですが、ずっと喉が黒いままだったり、全身が黒くなっていたりする場合はストレス過多や病気の可能性が考えられます。
・強いストレスを感じている
・健康状態に問題がある
・飼育環境の見直し(温度・湿度、ケージ内の配置、エサ)
・過剰な接触を控える
・動物病院を受診する
ご飯を食べない(体重の減少)
高齢になると代謝が落ちて食が細くなるのは、どの生き物にも共通して見られる症状です。
しかし、まだまだ元気な年頃なのにご飯を食べない、体重が減ってしまっている、という時には体調不良や消化不良、誤飲誤食を疑いましょう。
フトアゴヒゲトカゲは、エサの与え過ぎや室温の低下で消化不良を起こすことがあります。
また、エサの与え過ぎは肥満につながり、肥満は様々な病気を誘発してしまうので、太らないように気を付けなくてはいけません。
異物を誤飲・誤食した場合、便秘や腸閉塞を起こすこともあり、そのままにしていると危険なため、疑わしい時はすぐに病院へ連れて行ってあげましょう。
・エサの与え過ぎ
・栄養バランスの偏り
・ケージ内温度の低下
・異物の誤飲、誤食
・強いストレスを感じている
・給餌量の見直し
・給餌内容の見直し
・温度と湿度を適切に整える
・環境の見直し(ストレス原因を取り除く、トンネルなど安心できる隠れ場所の設置、など)
・動物病院を受診する
水を飲まない
皮膚の張り感がなくなり、目がくぼんで見えるようなときは脱水症状の可能性が大です。
フトアゴヒゲトカゲは視野が狭く、水がある場所を認識しづらい傾向があります。
飼い始めで、水飲み場の位置を覚えてくれるまではシリンジやスポイトで水分を与えるようにしましょう。
初期の脱水状態なら、水を与えるとゴクゴクと飲んでくれます。
しかし、シリンジなどで水を与えても飲んでくれないことがあり、これは症状が深刻であることを意味します。
・水が置かれている場所がわからない
・湿度が低すぎる
・水分を多く含む野菜を与える(小松菜、サニーレタスなど)
・シリンジやスポイトで水を与える
・適切な湿度に整える
・動物病院を受診する
目を閉じたまま動かない
夜から朝までの時間帯で一定のリズムで呼吸している場合は、ただ眠っているのだと思われます。
しかし、ぐったりして動かない場合や、普段活動的になるはずの昼間も目を閉じたまま動かない、あるいは目ヤニや鼻水も出ているような場合は体調不良を疑いましょう。
低体温症や熱中症、感染症、その他病気の可能性があります。
・飼育温度が低すぎる、または高すぎる
・不衛生な環境
・病気の個体との接触
・飼育環境の見直し(温度・湿度を適切にする、掃除を徹底する)
・2匹以上で飼育している場合、体調不良が疑われる個体とは隔離する
・動物病院を受診する
呼吸が乱れる
フトアゴヒゲトカゲは、平常時には1分間で20~30回ほど、一定のリズムで呼吸をしています。
呼吸数は個体差もあるので、自分のフトアゴヒゲトカゲちゃんの平常時の呼吸数を数えておくようにすれば、異常時にすぐ気付けるのでおすすめです。
口を開けるのは、熱を逃がして上がり過ぎた体温を調節するときや威嚇するときくらいで、普段の呼吸時には口を開けることはありません。
「呼吸が荒い」「口を開けて深呼吸を続ける」「異常な呼吸音が聞こえる」などでは肺炎や感染症、酸素不足などの可能性が考えられます。
一時的であればそこまで心配する必要はありませんが、この状態が長く続いているときや、他にも「エサを食べない」「体色が黒くなる」などの症状も出ているときにはなるべく早く動物病院を受診しましょう。
・強いストレスを感じている
・不衛生な環境
・栄養不足
・飼育温度が低すぎる、または高すぎる
・ストレスの原因を取り除く
・飼育環境の見直し(掃除の徹底、温度・湿度の調整など)
・動物病院を受診する
フトアゴヒゲトカゲは仮死状態?亡くなっている?確認方法を解説

爬虫類であるフトアゴヒゲトカゲは、エサの少ない寒い時期を乗り越えるためにブルーメーションと呼ばれる軽い冬眠状態になったり、ストレスが原因で仮死状態になったりすることがあります。
そのため、動かなくなったからといって「死んでしまった」と判断するのは早計です。
冬眠状態や仮死状態は、フトアゴヒゲトカゲにとって負担が非常に大きく、最悪の場合ではそのまま目覚めることなく死んでしまうこともあるため、飼育下ではさせないことが推奨されています。
万が一、ブルーメーションや仮死状態になってしまった場合は、適切な方法で起こしてあげましょう。
まずはどのような時にブルーメーションや仮死状態に陥るのか、次に死亡時との見分け方、最後にブルーメーションからの起こし方をお伝えします。
仮死状態に陥る原因は体温低下やストレス
●体温の低下
元々、乾燥した砂漠地帯に生息するフトアゴヒゲトカゲにとっては、日本の冬はかなり過酷な環境と言えます。
飼育温度が15℃を下回るとブルーメーション(軽い冬眠状態)に陥ってしまうため、とくに秋・冬・春は適温を保つことが非常に重要になります。
では、ケージ内を適温に保ってさえいれば良いのかと言うと、実際のところはそうでもないようです。
ケージ内を適温に保っていても、ケージが置かれている部屋の室温調整をしていなかったケースでは、フトアゴヒゲトカゲが冬眠してしまった例も多々見られました。
ケージ内を25~35℃に保ちながら、室温も下がり過ぎないようにする必要があります。
●過剰なストレス
「急激な環境の変化」「騒音」「過剰な触れ合い」などは、フトアゴヒゲトカゲにとって多大なストレスになります。
過剰なストレスは一時的な仮死状態を引き起こすこともあるため、できる限り原因は取り除きましょう。
仮死状態は一種の防衛本能であり、原因が解消されなければその後体調をさらに悪化させることにもなりかねません。
死亡確認では呼吸・体温・反応をチェック
●呼吸
仮死状態に陥っている際は、平常時と比べると呼吸数がとても少なくなりますが、呼吸しないわけではありません。
数分間、フトアゴヒゲトカゲちゃんの胸のあたりをじっと見つめて、動きがないかを確認してください。
まったく動きが見られない場合は、死亡している可能性が高いです。

▲数分間見つめて胸の動きがないか確認
●体温
フトアゴヒゲトカゲの日中の適正体温は36.5℃ほどで、夜間は30℃以下まで下がるそうです。
適正体温を大きく下回り、体が冷え切ってしまっている場合は死亡している可能性があります。
ただし、ブルーメーション(軽い冬眠)中は体温も外気温にあわせて下がるため、冬場は判断が難しく注意が必要です。
●反応
仮死状態に陥っていても、顔や手足に触れれば何らかの反応を見せてくれるはずです。
触れても全く反応が無い場合は、残念ながら亡くなっている可能性があります。

▲顔や手足に触れて反応を見る
*爬虫類の死亡確認はとても難しいです。自分では判断できないと思ったら、獣医師に診てもらうようにしましょう。
ブルーメーション(冬眠)からの起こし方
①ケージ内の温度を徐々に上げる
急激な温度の変化は、フトアゴヒゲトカゲに負担をかけることになります。
数日かけてケージ内を適温に戻すくらいのつもりで、ゆっくりとあたためてください。
②動き出したら水を飲ませる
ブルーメーション中のフトアゴヒゲトカゲは、水分もほとんど摂れていません。
脱水症状を起こさないように、目覚めたら水を飲ませてあげましょう。
③体調が安定したら消化に良い食べ物を与える
ブルーメーション中は、代謝が低くなり内臓機能も弱まっている状態です。
目覚めてからしばらくの間は、消化機能も通常通りには戻っていません。
目覚めた初日はエサを食べないこともあります。
様子を見て、ペットちゃんの体調が安定してきた頃を見計らって消化に良いフードを少量から与えましょう。
④経過を観察する
体力が一気に戻ることはないので、目覚めから数日は様子をよく観察してください。
「ぐったりしている」「ずっとご飯を食べない」「目がちゃんと開かない」などの異変がある場合は、すぐに獣医師に診せましょう。
フトアゴヒゲトカゲのエンゼルケア(遺体の保清処置)と安置方法

爬虫類であるフトアゴヒゲトカゲは、哺乳類と比べると遺体の傷む速度が速い傾向にあります。
きれいな姿で見送ってあげるためにも、死亡が確認された後は、速やかにエンゼルケア(遺体の保清処置)と安置をしてあげましょう。
エンゼルケア(遺体の保清処置)はペットちゃんへの最後のお世話
エンゼルケアとは、遺体を清潔にして生前のような姿に整えてあげる処置のことを言います。
亡くなったペットちゃんの尊厳を守ると同時に、感染症予防や飼い主様の心の整理にもなります。
①フトアゴヒゲトカゲちゃんの体勢を整える
フトアゴヒゲトカゲは通常、亡くなってから数時間で死後硬直が始まります。
体が伸び切ったままで硬直してしまうと棺に納まらなくなってしまうこともあるため、まずは体勢を整えてあげましょう。
目や口が開いている場合は優しく閉じて、尻尾は体に沿うように丸めてあげましょう。
②フトアゴヒゲトカゲちゃんの体を清拭する
よく絞ったタオルやウェットティッシュなどで、フトアゴヒゲトカゲちゃんの全身を丁寧に拭いてあげましょう。
とくに目や口、お尻周りは汚れやすいので忘れず清潔にしてあげてください。

▲絞ったタオルで体を丁寧に拭いてあげる
*濡れすぎてしまった場合は、乾いたタオルで拭き直してあげましょう。濡れたままでは遺体の傷みが進みやすくなります。
適切な冷却・安置で1~3日ほどきれいな姿を保てる
適切に冷却と安置をすれば、夏場で1~2日ほど、冬場で2~3日ほどきれいな姿を保ってあげることができます。
①棺を準備してフトアゴヒゲトカゲちゃんを寝かせる
段ボール箱など、ペットちゃんの遺体を余裕をもって納めることができる大きさの箱を用意します。
その中にペットシーツやバスタオルを敷きましょう。
そこへフトアゴヒゲトカゲちゃんを優しく寝かせてあげてください。

▲棺の中にタオルを敷いてペットちゃんを寝かせる
*遺体からは体液や排泄物が漏れてくることがあります。こまめに確認して、汚れていたら拭き取り、ペットシーツやタオルは取り替えましょう。
②フトアゴヒゲトカゲちゃんの遺体を冷やす
保冷剤やドライアイスを布で包み、フトアゴヒゲトカゲちゃんの遺体の周りに置きましょう。
とくに傷みやすい頭部や腹部は重点的に冷やしてください。

▲布で包んだ保冷剤をペットちゃんの周りに置く
*遺体に水滴が付くと傷みの原因になります。保冷剤は遺体に遺体に直接触れないようにしましょう。
*ドライアイスを使用する場合は、素手では触れず、部屋の換気を徹底し、棺は密封しないでください。
③棺を冷暗所に安置する
夏場なら冷房が効いた部屋、冬場なら煖房を入れていない部屋に棺を安置します。
この時、直射日光やエアコンの風が棺に当たらないように注意してください。
火葬までの間は、ペットちゃんを静かに眠らせてあげましょう。

▲お花やフードを供えてあげるのもおすすめ
ペットちゃんとゆっくりお別れができるかけがえのない時間でもあります。
お花や好物のおやつを供えてあげる、今までの感謝を伝える、などして過ごしてください。
フトアゴヒゲトカゲの葬送への備え|火葬・供養方法の選択

愛するペットちゃんとの別れを経験した直後に、冷静でいられる飼い主様はほとんどおられないでしょう。
大切な存在を丁寧に弔ってあげたいのであれば、気持ちに余裕のある今の内から葬送方法を考えておくことが大切だと筆者は思います。
ペットの遺体は、私有地への埋葬が法律で認められています。
しかし、フトアゴヒゲトカゲは外来生物であるため、日本の生態系や自然環境への影響がないとも言い切れず、そのままの状態で埋葬することは推奨できません。
私有地への埋葬を行うにしても、火葬してから遺骨の状態でするのが望ましいと言えます。
ペットちゃんの火葬は、「自治体」「訪問ペット火葬業者」「ペット霊園」のいずれかに頼むことができます。
費用面やどこまで対応できるかがそれぞれ異なるため、「ペットちゃんをどんな風に見送りたいか」「遺骨はどのように供養するか」を決めておくと選択しやすくなるのでおすすめです。
火葬は「自治体」「訪問ペット火葬業者」「ペット霊園」で依頼できる
●「自治体」は安価で火葬ができる
行政が運営しているためトラブルの心配なく利用できて、また安価なのも嬉しいポイントです。
費用を抑えたいとお考えの飼い主様にはピッタリの方法と言えるでしょう。
ただし、基本的には他のペットや野生動物たちと一緒に合同火葬されるため返骨できない自治体が多く、中には一般廃棄物と一緒に焼却されるところもあります。
遺骨の手元供養や自宅埋葬、ペット霊園への埋葬を検討している方は、「訪問ペット火葬業者」や「ペット霊園」を選択するのが良いでしょう。
*少ないですが、返骨や霊園への埋葬に対応している自治体もあります。
地域によって対応はまちまちなので、事前にホームページなどを確認しておきましょう。
●「訪問ペット火葬業者」は時間・場所にとらわれない自由なお見送りができる
ペット用火葬炉を搭載した専用車で火葬を行うため、飼い主様の臨む場所まで来てもらうことができます。
土日・祝日や夜間・早朝での火葬にも対応している業者が多く、忙しい飼い主様や家族みんなで揃って見送りたいという飼い主様に人気があります。
費用は自治体と比べるとやや高額になりますが、その分できることも多いです。
ペットちゃんだけを個別で火葬する、拾骨や返骨ができる、メモリアルグッズを購入できる、など自由度の高さが魅力と言えます。
●「ペット霊園」は火葬から埋葬までをその日中に終えられる
斎場、火葬場、納骨堂(霊座)、墓地が同じ敷地内にあり、葬儀から埋葬までを一日で終えることができるのがペット霊園の特徴です。
年忌法要や供養祭を行う霊園も多く、手厚い供養が受けられます。
ただし、費用が高額になりがちな点と、敷地面積の関係で郊外にあることが多く、車を持たない人には行きづらい点は考慮しておく必要があります。
供養は「手元供養」「自宅埋葬」「ペット霊園への納骨」「自然散骨」から選ぶ
●手元供養(祭壇、遺骨アクセサリーなど)
自宅にペットちゃんの骨壺や遺影を祀ったり、専用のカプセルに納骨してアクセサリーとして身につけたりする供養方法で、いつでもペットちゃんを近くに感じることができます。
四十九日を迎えてからペット霊園に納骨したいとお考えの飼い主様にもおすすめです。
●自宅埋葬(私有地、プランター)
私有地、またはプランターにペットちゃんの遺骨を埋葬する供養方法で、いつでもお墓参りができるという利点があります。
墓標代わりに植物を植えて育てることもできるため、お世話好きの飼い主様に人気があります。
●ペット霊園への納骨
室内型の墓地である納骨堂(霊座)と、屋外の墓地から納骨先を選ぶことができます。
屋外墓地には合同墓地(他のペットちゃんたちと一緒に埋葬)と個別墓地(ペットちゃんだけを個別で埋葬)があり、個別墓地の場合は墓石もオリジナルで作ることができるようです。
●自然散骨
「大自然にペットちゃんを還してあげたい」という飼い主様に選ばれている散骨は、その名の通り、海や山などに遺骨を撒く供養方法です。
ただし、遺骨は粉骨(遺骨をパウダー状にすること)しておかなくてはならず、行える場所も限られます。
自治体によっても散骨のルールが異なるため、行う場合は下調べが欠かせません。
行政の許可を得て散骨を行っている専門業者に依頼すれば、ルールに則って安全に執り行ってくれるので安心です。
まとめ
フトアゴヒゲトカゲが亡くなる前には以下のような症状が現れることがあります。
・体色が黒くなり色が戻らない
・ご飯を食べない(体重の減少)
・水を飲まない
・目を閉じたまま動かない
・呼吸が乱れる
先天的な体質や病気の影響で体調を崩す子もいますが、フトアゴヒゲトカゲの場合、飼育状況が要因となって体調を崩すケースが多いようです。
とくに、「温度・湿度」「給餌量・内容」「紫外線不足」などには細心の注意を払ってあげましょう。
それでも、上記のような症状が現れた場合は、原因を見つけて速やかに改善してください。
また、対策を講じても体調が回復しない場合は、すぐに動物病院へ連れて行き適切な治療を受けさせてあげましょう。
愛するフトアゴヒゲトカゲちゃんと充実した時間を共に過ごすためにも、飼育環境を整えて元気に長生きできるようにしてあげてくださいね。
そして、いざお別れをするときには悔いなくお見送りができるように、火葬や供養方法、安置の仕方などもこの機会に確認しておくことをおすすめいたします。
この記事の執筆者

ペット火葬
ハピネス 編集部 S・A
愛犬・愛猫・愛鳥など8匹以上を見送った経験を持ち、現在も愛犬と暮らす動物愛好家。初代愛犬を満足に供養できなかった経験からペット火葬ハピネスへ入社。あたたかなペット葬儀のための情報を発信。私生活では動物保護ボランティアへの支援を行っている。