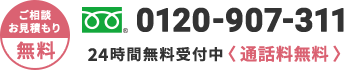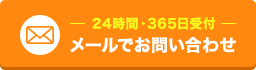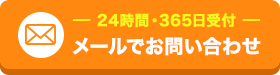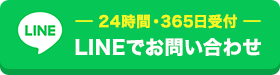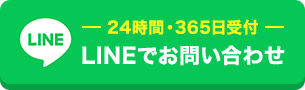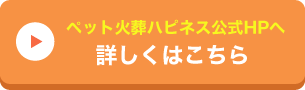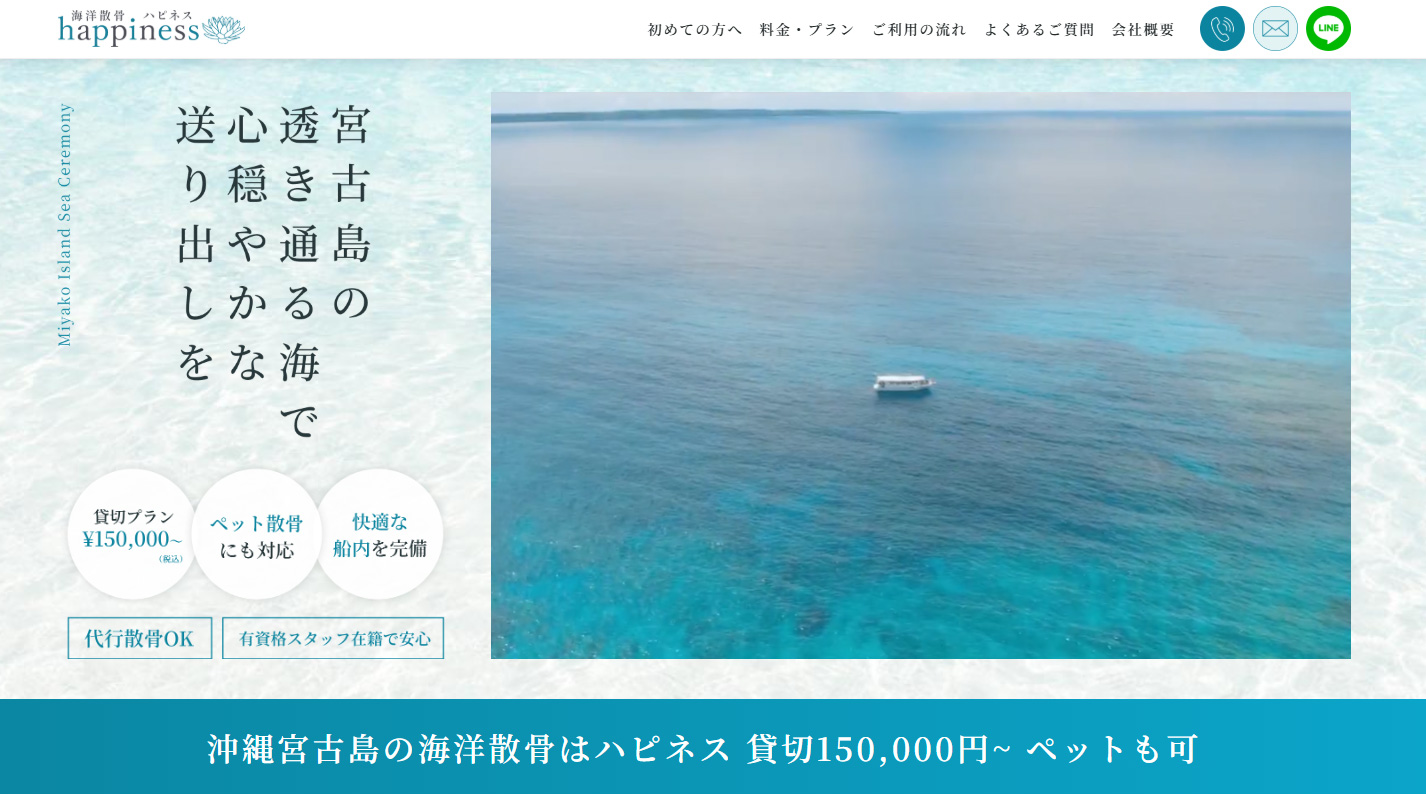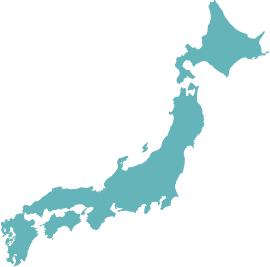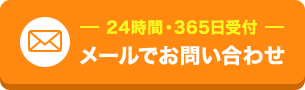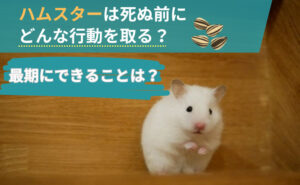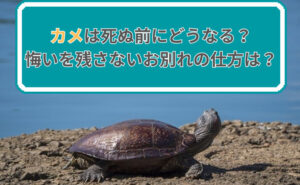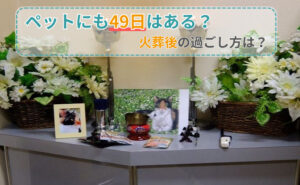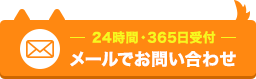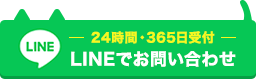デグーは、愛嬌のある仕草や可愛らしい顔立ちが特徴で、人慣れも比較的しやすく、一緒に暮らす飼い主様も増えている人気のペットです。
「可愛いデグーとずっと一緒に暮らしたい」というのが飼い主様の願いだと思いますが、その寿命は5~8年ほどで、中には突然死してしまう子もいるようです。
家族同然のデグーに健康で長生きしてもらうため、そして最後の時まで悔いなく見送ってあげるために、ぜひ飼い主様にはしていただきたいことがあります。
それは以下の4つです。
①デグーの突然死の原因を知り、対策する
病気やケガ、ストレスなど突然死につながる原因がわかれば、健康を保つための対策ができます。
②デグーの異変を見逃さない
行動や食事量などの小さな変化を見つけられれば、体調の悪化にいち早く気付き治療を受けさせることができます。
③見送り方や供養方法を考えておく
その時になってからでは冷静な判断は難しくなるものです。今の内からしっかりと考えておけば、焦ることなく対応できます。
④エンゼルケアや安置の方法を確認しておく
ペットちゃんへの最後のお世話が丁寧にでき、きれいな姿で送り出してあげることができます。
当記事では、デグーに多い死因とその対策、最期を悔いなく迎えるための準備、そして亡くなってしまった際の安置方法まで詳しく解説いたします。
愛するデグーと幸せな日々を過ごすため、そして安らかに旅立ってもらうためにも、生前にできることはすべて行い、いざお別れの時が来ても慌ててしまわないようにしましょう。

この記事の監修者
高間 健太郎(獣医師)
大阪府立大学農学部獣医学科を卒業後、動物病院に勤務。診察の際は「自分が飼っている動物ならどうするか」を基準に、飼い主と動物の気持ちに寄り添って判断するのがモットー。経験と知識に基づいた情報を発信し、ペットに関するお困り事の解消を目指します。
デグーの死につながる原因は?|病気・誤食・飼育環境・ストレス

デグーの中には、平均寿命を超えて10年以上もの長生きをする子もいます。
できれば愛するペットちゃんも同じように健康で長生きしてもらいたいですよね。
そのために、デグーの死につながってしまう可能性のある原因をできるだけ排除するように対策しましょう。
デグーの死因となり得るのは次の4つです。
・病気
・誤食
・飼育環境
・ストレス
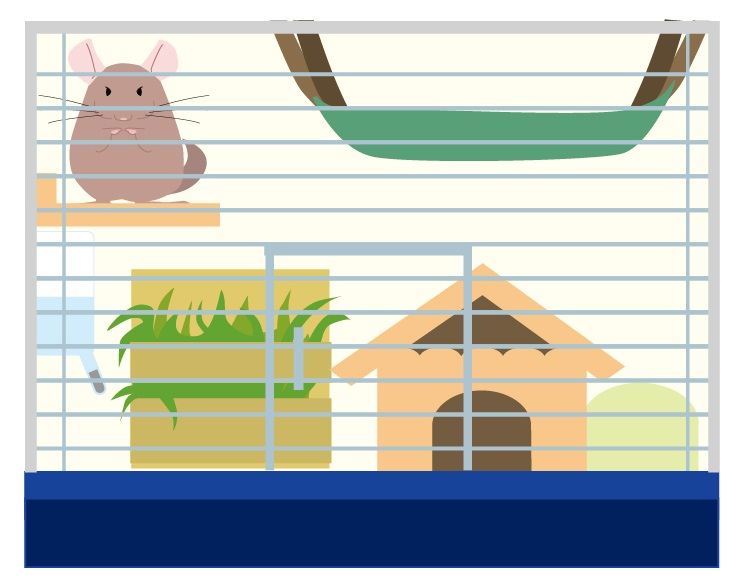
それぞれを詳しく見ていきましょう。
デグーに多い病気とは?死因になりやすい病気とその対策
デグーは、生まれ持った特性から「糖尿病」になりやすいですし、また暑さ・寒さにも弱いなど、病気にならないためには気をつけなくてはいけないことが多々あります。
もちろん対策したからと言って、病気になることを完全に防ぐことができるわけではありませんが、予防効果を高めることはできます。
まずは、デグーがかかりやすい病気を知り、予防対策をしっかりと行いましょう。
●糖尿病
デグーは他の生き物と比べてインスリンの働きが弱く、糖質を摂った際に血糖値が上がりやすいため、糖尿病になりやすいのです。
糖尿病を発症すると、「体重の減少」「過剰な飲水・排尿」「食欲不振」「視力低下」などの症状が出ます。
放置すると心血管疾患や腎不全などの合併症を引き起こし、死亡する場合があります。
糖分の多い食事
低糖質・高繊維の食事を心掛ける
(果物、かぼちゃなど糖分の多いものは極力与えないようにする)
●不正咬合(ふせいこうごう)
デグーの歯は一生伸び続けるという特徴があります。
通常は堅い物をかじったり、高繊維質の食事をすることで歯が削られ適切な長さに保たれます。
しかし、削られる機会が少なく、異常に伸びてしまうと上手く食事ができなくなり食欲不振や体重減少につながります。
また口が上手く閉じられずよだれを垂らすようになります。
適度な堅さのあるかじれる物が少ない
・専用のかじり木を与える
・定期的な歯のチェックをする
●熱中症
デグーは野生下では、熱帯気候で標高1,200m以上の山地に生息しているため、日本の高温多湿な環境は大の苦手です。
発症すると「体温が高くなる」「ぐったりする」「呼吸が早い・または浅い」などの症状が見られ、酷い場合は「意識障害」や「けいれん」を起こすこともあり命の危険があります。
・高温多湿な環境
・直射日光に長時間当たる
・室温、湿度を適切に保つ
・小まめに水分補給させる
・デグーが暑さから逃げられるように、ケージ内にも涼しい場所を用意する
・症状が出ている場合は、すぐに涼しい場所へ移動させて体を冷やし、動物病院を受診する
●低体温症
デグーは暑さに弱いですが、寒さにも弱い動物です。
適温以下の環境に長時間置かれると体が冷えて低体温症を発症します。
「体温低下」「震え」「ぐったりする」「動きが極端に遅くなる」などの症状が見られ、そのまま放置すると最悪の場合は死に至ります。
ケージの隅っこで丸まって動かないようなときは寒がっている可能性が高いので要注意です。
・低気温
・エアコンの冷たい風が直接当たる
・体が濡れたままになっている
・室温・湿度を適切に保つ
・エアコンの風が直接当たらないようにする
・デグーが寒さから逃げられるように、ケージ内にも暖かい場所を用意する
・症状が出ている場合は、暖かい場所へ移動させ、じわじわと体をあたため、動物病院を受診する
*急激に温めるのはNG!デグーの体に負担となり逆効果です。必ず時間をかけてゆっくりと温めましょう。
●食道閉塞
食道閉塞とは、食べ物がデグーの喉に詰まることです。
「よだれが出る」「食欲不振」程度で済めば良いのですが、「呼吸困難」や「窒息」になることもあり危険です。
ドライフルーツやナッツ類などの乾燥した食べ物が喉に引っかかる
ドライフルーツやナッツ類よりも、生野菜を与える
*ただし糖分の多いものは与え過ぎないようにしてください。
●肥満
適正体重以上に太ってしまうと、関節に負荷が掛かりケガをしやすくなります。
また、心臓、肝臓などの内臓や血管にも悪影響を及ぼし、放置すると様々な合併症により命の危機に陥ることもあります。
・種子やナッツ、ドライフルーツなどの高カロリーの食べ物の与え過ぎ
・運動不足
・歩き回れる広い場所での部屋散歩、運動用の遊び道具の設置など、適度な運動ができる環境を作る
・バランスの取れた食事を心掛ける
・高カロリーのおやつは極力与えない
デグーは何でもかじってしまう!誤食・誤飲に注意
デグーは、生涯歯が伸び続けるので、適切な長さを保つために何でもかじってしまいます。
その際、デグーにとって毒となるものを食べてしまう、電気コードをかじって感電する、などの事故が起こることがあります。
ケージの近くに危険なものを置かない、部屋んぽ(部屋の中を散歩)中は目を離さない、といったことに注意して誤食・誤飲を防ぎましょう。
・ネギ類(長ネギ、玉ねぎ、ニラ、ニンニクなど)
・ジャガイモの芽、葉、茎
・サトイモ
・アボカド
・チョコレート
・牛乳
・糖分の多い果物
・ハーブ類
・人間の食べ物 など

・電気コード
・電池
・タオルなどの布片
・観葉植物
・プラスチック製品
・小さな部品
・アクセサリー類
・人間の薬、サプリメント など

暑いのも寒いのも苦手!デグーにあった飼育環境に整える
デグーに健康に過ごしてもらうためには、デグーにあった環境に整えることが大切です。
私たち人にとって快適な環境が、デグーにとってはそうではないことを理解し、きちんと対応してあげましょう。
●温度・湿度
デグーにとっての適温は20~25℃ほど、湿度は50%前後が理想とされています。
理想の飼育環境を保てるように、ケージは日光やエアコンの風が直接当たらない、静かで落ち着ける場所に設置し、室温・湿度を調整します。
もちろん個体差があり、少し寒がりの子もいれば暑がりの子もいるため、様子を見ながら最適な温度と湿度を保ってあげましょう。
また、デグー自身でちょうど良い温度の場所へ移動できるように、ケージ内に暖かい場所や涼しい場所を用意するようにしてください。
●ケージ内のレイアウト
デグーは山脈の傾斜部に生息しているため、上下運動ができるようにケージ内をレイアウトしてあげましょう。
運動不足にならないよう十分に動き回れる大きさのケージを用意してください。
遊具を設置する場合は、ケガにつながるようなものは避け、落下事故が起きにくい配置を心掛けましょう。
●砂場の設置
デグーにとって砂場は、私たちにとってのお風呂のような存在です。
体の汚れを落とすだけでなく、リラックスしたりストレスを解消したりする大切なものです。
週に1~2回ほどの頻度で砂浴びをさせてあげましょう。
常設すると、誤って砂を食べてしまう子もいるようなので、砂浴びするときだけ砂場をケージ内に入れるようにして、飼い主様が見ている中で行うのがおすすめです。
デグーはストレスに弱い!
デグーは集団で暮らす生き物のため、臆病で寂しがり屋な性格の子が多いようです。
ストレスを感じやすく、脱毛症などの病気になったり弱ったりすることもあるので注意しましょう。
●単頭飼いの場合
デグーは、元々群れで生活する動物のため、単頭飼いだと寂しさを感じやすい傾向があります。
飼い主様とコミュニケーションを取れる時間を十分に取り、不安を感じさせないようにしてあげることが大切です。
●多頭外の場合
人同士でも相性の良し悪しがあるように、デグー同士でも相性の良し悪しがあります。
とくにオス同士の場合、縄張り意識から喧嘩をしてしまうこともあり、大ケガをしてしまうかもしれません。
筆者の友人も兄弟のデグーを飼っていましたが、成長して縄張り意識が芽生えたのか、ある日を境に喧嘩を繰り返すようになってしまったそうです。
こればかりは一緒に飼育してみないとわかりませんし、もし相性が良くないと判明した場合は速やかにケージを別々にしてあげましょう。
また、オスとメスのペアの場合は、当然子供が産まれる可能性があります。
デグーは3カ月ほどの妊娠期間を経て、1回の出産で3~10匹の子供を産みます。
度重なる出産はメスにとって負担になりますし、何より多頭飼育崩壊にもつながる可能性があるため、繁殖を望まない場合は別々に飼育するほうが良いでしょう。
●騒音・振動に注意
デグーは聴覚が優れていて、また臆病な性格でもあるため、大きな音や振動にもとても敏感です。
掃除機やテレビの音、車のクラクション、サイレン、電車の振動などにストレスを感じます。
ストレスを感じると「キーキー」と甲高い声で鳴いたり、毛を逆立てる、過剰にグルーミングをする、自分で毛を抜くなどの問題行動をするようになります。
ケージは静かな場所に設置し、大きな音や振動からは遠ざけてあげるようにしましょう。
デグーが亡くなる前に見せる行動や症状は?毎日観察して異変を察知

「デグーは突然死が多い」と言われますが、これはデグーには弱っている姿を隠そうとする習性があるため、異変に気付きにくいことが原因と考えられます。
少しの異変にも気付けるようになれば、取り返しがつかなくなる前に助けられるかもしれません。
ここでは、デグーが亡くなる前に見せる行動や症状をご紹介し、また健康チェックのために毎日観察すべきポイントを解説します。
デグーが亡くなる前の行動・症状と毎日のチェックポイント
デグーが亡くなる前には、行動に変化が見られたり、死亡直前には様々な症状が現れたりすることがあります。
●食欲がなくなる
老化や病気などで体力や内臓機能が落ちると、食事をする意欲が低下してしまうことがあります。
エサをふやかすなどすれば食べてくれることもありますが、それも徐々にできなくなってきます。
毎日、「甘いものを食べ過ぎていないか」「食事量が減っていないか」を確認してください。
また、幼少期、青年期、壮年期、老齢期と、年齢にあった食事内容に調整しましょう。
●じっとして動かなくなる
老化が進むと、人と同様活動量が減り、寝ている時間が増えてきます。
また病気やケガで動くのがつらい場合も、じっとして動かないことがあります。
デグーを驚かせないように気をつけながら、優しく抱っこして皮膚に異常がないか、毛並みは悪くなっていないか、体にしこりがないか、また痛がる様子はないかを確認してください。
老化の場合は自然なことですが、病気やケガの可能性がある場合は、すぐに獣医師に見せることが大切です。
●体が冷たくなってくる
身体機能が弱っていると、体をあたたかく保つことが難しくなり、体温が低下してきます。
優しく触れたときに体が冷たくなっていないか確認しましょう。
健康なデグーの平熱は38~39℃ほどです。
38℃を下回るような場合は低体温症になっている可能性もあるため注意しましょう。
●呼吸数の減少、呼吸が荒く、または浅くなる
呼吸が少なくなる、呼吸が浅く、荒くなるなど、デグーが苦しそうに息をしている場合は、かなり危険な状態と言えます。
喉に何か詰まらせている可能性もありますし、老化や病気により満足に呼吸できないほど弱っていることも考えられます。
健康なデグーの呼吸数は平均75回(1分間)だそうです。
いつもと呼吸の仕方が違うと感じたら、1分間を目安に呼吸数を数えるようにし、異常があれば獣医師に診せましょう。
毎日、デグーの様子を観察して異変が見られたらすぐに動物病院へ連れて行ってあげられるようにしましょう。
デグーには半年に1回を目安に健康診断を受けさせ、高齢になったら獣医師と相談して健診の頻度を増やすなど調整するのが望ましいです。
また、デグーの健康チェックをスムーズに行うためにも、日頃から少しずつ根気よく接するようにして、飼い主様の手に慣れさせておきましょう。
デグーが亡くなる前に考えておきたいこと①|見送り方を決める

大切な家族であるデグーが亡くなってしまったときに、冷静でいられる飼い主様はほとんどおられないでしょう。
その時になってから、ペットちゃんをどうやって天国へ旅立たせてあげるかを考えるのはなかなか難しいと思います。
落ち着いてじっくりと考えられるように、ペットちゃんの生前からお見送りの仕方は目星をつけておくのがおすすめです。
デグーの見送り方には「自治体の引き取り」「訪問ペット火葬業者で火葬」「ペット霊園で火葬」「私有地・プランターへの埋葬」の4つがあります。
以下に、それぞれの特徴を解説します。
「自治体の引き取り」は費用を抑えられるが…
利用規則や料金、対応は地域によって異なりますが、自治体ではペットちゃんの遺体を引き取り火葬してくれます。
高いところでも数千円程度と安価で利用できるのが特徴で、費用を抑えたい飼い主様にはぴったりです。
しかし、ほとんどの自治体で火葬への立ち会いや返骨には対応しておらず、思い通りのお見送りができない可能性もあります。
火葬後の遺骨は他の一般ゴミと一緒に埋め立てられる自治体も多く、中にはゴミと一緒に遺体を焼却するところもあるため、後悔しないためにも利用する前にどのような対応になるかを調べておくことを推奨します。
「訪問ペット火葬業者で火葬」は好きな場所でお見送りできる
訪問ペット火葬業者は、その名の通り、飼い主様の指定する場所までペット用火葬炉を搭載した車で訪問し、その場で火葬してくれます。
小さなお子様や高齢者がおられるご家庭や、急な外出が難しい飼い主様にはとても便利なサービスです。
火葬への立ち会いや拾骨、返骨ができる火葬プランもあるため、「最後までそばにいてあげたい」「遺骨を自宅で供養したい」という飼い主様に人気があります。
費用は自治体利用と比べるとやや高額になりますが、時間や場所の融通も利き、ペットちゃんを丁寧に見送れるため、近頃ではこの方法を選ぶ飼い主様が増加しています。
・合同火葬(他のペットちゃんと一緒に火葬):5,500円(税込)~
・個別火葬(スタッフに任せてペットちゃんだけを火葬):13,200円(税込)~
・個別火葬プレミアム(飼い主自ら火葬に立ち会いペットちゃんだけを火葬):16,500円(税込)~
・自宅セレモニー葬(自宅でお別れのセレモニーを行い、飼い主自ら火葬に立ち会いペットちゃんだけを火葬):29,700円(税込)~
「ペット霊園で火葬」は人と同じような葬儀が可能
ペット霊園は、敷地内に火葬場と納骨堂・墓地があるところが多く、ペットちゃんの葬儀から火葬、埋葬までを一連の流れで行うことができます。
僧侶による読経を行っているところもあり、人の葬儀さながらのセレモニーを執り行うことができるのが特徴です。
訪問ペット火葬業者と同じく、拾骨や返骨ができる火葬プランもあります。
費用は4つの中で1番高額となり、立地的にアクセスしにくいところが難点にはなりますが、「人と同じように弔ってあげたい」「遺骨はそのまま霊園に納めたい」という飼い主様にはおすすめの方法です。
・合同火葬(他のペットちゃんと一緒に火葬する):平均11,000円~
・一任個別火葬(スタッフに任せてペットちゃんだけを火葬する):平均19,500円~
・立会個別火葬(飼い主自ら火葬に立ち会いペットちゃんだけを火葬する):平均37,000円~
*費用相場は複数のペット霊園の料金を平均して算出しています
「私有地・プランターへの埋葬」は火葬後にするのがベスト
自宅の庭やプランターにペットちゃんのお墓を作ることは、ひと昔前までは一般的な方法でした。
ペットちゃんをいつもそばに感じられて、好きなタイミングでお墓参りできる点や、費用がほとんどかからない点がこの方法の魅力です。
しかし、注意すべき点も多数あるので、行う場合は注意が必要です。
まず、ペットちゃんの遺体の埋葬は、私有地やプランターで行う場合のみ許可されています。
悲しいことですが、ペットちゃんの遺体は一般廃棄物として扱われるため、私有地以外に埋葬する行為は不法投棄とみなされ罰則の対象になるのです。
次に、ペットちゃんの遺体は、土に還る過程で腐敗臭の発生や、虫が湧いてしまうこともあります。
野生動物に掘り返される恐れもあるため、土に還るまでの約10年程は管理が欠かせません。
また、庭などに埋葬した場合は、気軽に引越しや土地の売却ができなくなるので、その点も心得ておきましょう。
埋葬の問題を解消するためには…
埋葬に伴う問題をできるだけ解消したいなら、ペットちゃんの遺体を火葬して遺骨にしてから行うのがおすすめです。
遺骨の状態であれば臭いや虫の発生を防ぐことができますし、土に還るまでの時間も短くできます。
デグーが亡くなる前に考えておきたいこと②|供養方法を決める

火葬後の遺骨をどのように供養するかも、今の内から考えておきましょう。
遺骨の供養方法で代表的なのは以下の4つです。
・手元供養(祭壇、遺骨アクセサリーなど)
・自宅埋葬(私有地、プランター)
・ペット霊園への納骨・埋葬
・自然散骨
遺骨を分骨すれば、例えば「一部だけ返骨してもらい遺骨アクセサリーにして身につけ、残りは霊園に納骨する」など、飼い主様の意向に沿って柔軟に供養することもできるので、以下の説明を参考にご検討ください。
手元供養(祭壇、遺骨アクセサリーなど)
「ペットちゃんと離れるのは寂しい」「ずっと近くで供養したい」という飼い主様に選ばれているのが手元供養です。
室内に、遺骨やペットちゃんの写真を祀り祭壇を作る方法や、遺骨をカプセルに収めてキーホルダーやアクセサリーにして身につける方法などがあります。
ペット用の位牌やメモリアルボックスなど、供養のためのグッズも豊富で、一見すると遺骨が収められているとはわからない骨壺カバーなども販売されています。
自宅埋葬(私有地、プランター)
自宅埋葬は、いつでもお墓参りができる点と、植物を植えればペットちゃんにしてきたようにまたお世話ができる点が魅力で、お世話好きな飼い主様に人気の供養方法です。
墓石や墓標をペットちゃんのために手作りしたり、セミオーダーで購入したりする飼い主様も多いようです。
ペット霊園への納骨・埋葬
ペット霊園では、日常的な管理を任せることができるうえに、年忌法要や供養祭も行われるため、行き届いた環境で丁寧な供養ができます。
「四十九日までは手元供養をして、その後ペット霊園へ納骨したい」といった要望にも対応してもらえるので相談してみるのも良いでしょう。
また、ペットちゃんと一緒に入れるお墓を提供している霊園もあるため、「いずれは一緒に」とお考えの飼い主様はぜひ探してみてください。
自然散骨
散骨は、海や山などの大自然にペットちゃんを還してあげたい、という飼い主様に選ばれている供養方法です。
散骨を行うには、遺骨をあらかじめ粉骨しなくてはならず、またどこでも勝手に散骨できるわけではないため入念な下調べが必要です。
自分の私有地や許可を得た場所で行うのはもちろん、周囲の人にも配慮するのがマナーです。
散骨できる場所を探すのは容易ではないため、きちんと許可を得て運営している専門業者に依頼するのが良いでしょう。
デグーが亡くなったらエンゼルケアと安置をしてお別れの準備をする

お別れの時が来てしまったら、悲しみから気持ちが塞ぎこんでしまうかもしれません。
それでも、愛するペットちゃんがきれいな姿で天国へ旅立てるよう、心を強く持ってエンゼルケア(遺体の保清処置)と安置をしてあげましょう。
正しい方法で行えば、夏場で1~2日、冬場で2~3日ほどきれいな姿を保つことができます。
以下にデグーのエンゼルケアの仕方と安置方法をご紹介しますので、その時に備えて当ページをブックマークしておくことをおすすめします。
デグーのエンゼルケア(遺体の処置)のやり方
①デグーの体勢を整える
まずはデグーをペットシーツやタオルなどの上に寝かせ、眠っているような楽な体勢に整えてあげましょう。
目や口が開いている場合は、優しく閉じてあげてください。
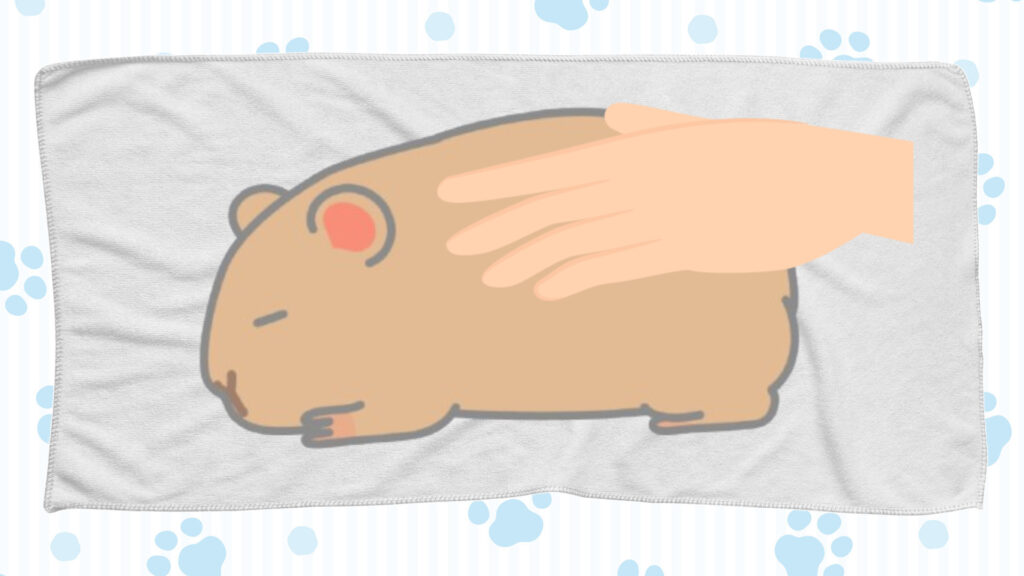
②汚れを拭き取り清潔にする
ペット用ウェットシートや濡らしてよく絞ったタオルなどで、体全体を拭いて清潔にしてあげましょう。
とくに目や口、お尻周りは汚れやすい場所です。
デグーが亡くなって体の力が抜けると排泄物が漏れ出てしまうこともありますので、こまめに確認して拭いてあげてください。

③毛並みを整える
毛並みが乱れていたら、優しくブラッシングをして毛並みを整えてあげましょう。
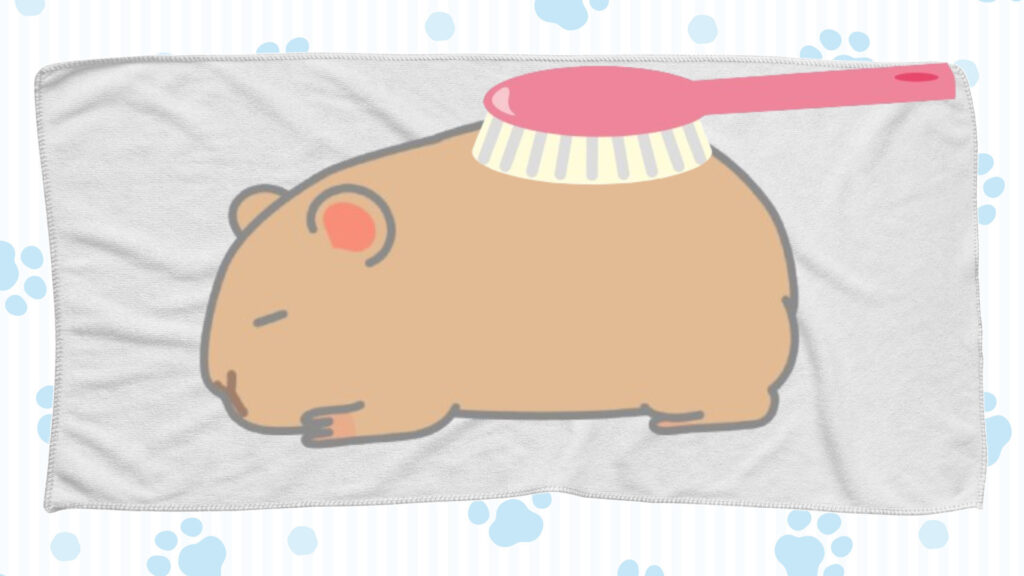
デグーの遺体の安置方法
①棺を準備する
デグーの体が余裕をもって納まるサイズの箱を用意します。
箱は、火葬時に支障のない紙製やペット専用の棺が良いでしょう。
棺の中にはペットシーツやタオルを敷いてください。

②デグーの遺体を棺に納める
デグーの遺体をタオルなどの清潔な布で包み棺の中に寝かせます。
または、デグーの遺体を棺に寝かせ、タオルなどの布を掛けてあげるのでも構いません。

③デグーの遺体を保冷剤で冷やす
保冷剤を遺体の周りに置いて冷やします。
この時、頭やお腹など傷みが進みやすい場所を重点的に冷やすようにしてください。
また、保冷剤は溶けきる前に新しいものに交換しましょう。
*遺体を布で包まない場合は、保冷剤を布で包んで遺体が濡れないようにしましょう。

まとめ
デグーが亡くなる前にしてあげられることはたくさんあります。
健康で長生きできるように飼育環境や給餌を適切にすることはもちろん、突然死につながりそうな要因をできるだけ取り除きましょう。
また、日頃からペットちゃんの観察を欠かさず、異変があればすぐに気付けるように心掛けてください。
いずれ訪れるであろうお別れの日を見越して、お見送り方法や供養方法を考えておくことも大切です。
そして、最期の時が近づいてきたら、できるだけそばにいて優しく声をかけてあげてください。
デグーは寂しがり屋な性格の子が多いため、飼い主様がそばにいてくれたら安心して旅立てるのではないでしょうか。
当記事が、飼い主様と愛するペットちゃんとのかけがえのない日々の助けになりますことを願っています。
この記事の執筆者

ペット火葬
ハピネス 編集部 S・A
愛犬・愛猫・愛鳥など8匹以上を見送った経験を持ち、現在も愛犬と暮らす動物愛好家。初代愛犬を満足に供養できなかった経験からペット火葬ハピネスへ入社。あたたかなペット葬儀のための情報を発信。私生活では動物保護ボランティアへの支援を行っている。